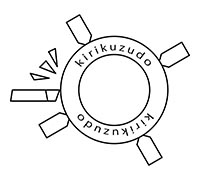切屑堂 kirikuzudo
ブログ: 2024/12/29 『JAXA長期ビジョン -JAXA2025- 20年後の日本の宇宙と航空』を読む(その4)
前回(その3)
各論の2回目です。
前回は実用衛星(宇宙利用推進本部あるいは第一宇宙技術部門)の範囲でした。
<今回読んでいく対象領域>
今回は「長期ビジョン全体ロードマップ」から対象領域
2.宇宙観測/太陽系探査
3.月探査・利用
を選んで見ていきたいと思います。
<ロードマップ記載>
ロードマップには
2005~2010年
C「宇宙望遠鏡の展開と多様な挑戦的科学ミッションの立上げ」
D「小惑星への到達/太陽と月の精査」
E「月探査の技術開発及び実証」
2010~2015年
C「宇宙望遠鏡観測の全波長域への展開」
D「木星型惑星探査の開始と地球型惑星の探査」
E「月探査の技術開発及び実証」
2015~2024年
C「宇宙で最初の銀河・ブラックホールの観測」
C’「太陽系外の地球型惑星での生命の徴候の探索」
D「太陽系外への到達と地球型惑星の精査」
E「月探査・利用技術の蓄積」
2025年
C,D「宇宙科学のトップサイエンスセンター」
E「月面拠点の構築と利用のための技術の確立」
とあります。
<「長期ビジョン」内の記載>
2章の「長期ビジョン」ではPage.10~11の
「(2)知の創造と活動領域の拡大への貢献 」が該当する部分です。
前回の実用衛星からするとわりと挑戦的な文言が並んでいますね。
「多様な波長域の宇宙観測と独自の手法による太陽系探査」
「月面拠点の構築と利用のための技術を確立」
「月やラグランジュ点を人類活動の場として活用する"深宇宙港構想"の実現」
<「ビジョンの実現に向けて」内の記載>
3章の「ビジョンの実現に向けて」ではPage.22~29が該当します。
さすがに多いですね。
ここでは
「(1)宇宙観測・太陽系探査」(Page.22~25)
「(2)月の探査と利用」(Page.26~29)
の2つの大項目に分けられています。
「(1)宇宙観測・太陽系探査」の中では当時、計画されたり運用されたりしていた下記の探査機や衛星について言及されています。
・ASTRO-E II(X線天文衛星)
2005年7月10日にM-V F6で打上。2015年6月1日に運用終了。
ブラックホールの周囲の物質の運動や降着流の詳細な観測、
ペルセウス座銀河団の外縁部を観測、高温プラズマのX線分光観測により
宇宙物理学の分野に大きく貢献。
・ASTRO-F(赤外線天文衛星)
2006年2月22日にM-V F8で打上。2011年11月24日に運用終了。
原始銀河の探索や星生成領域の高感度赤外線観測、
原始惑星系円盤からの放射観測により、宇宙物理学の分野に大きく貢献。
・SOLAR-B(太陽観測衛星)
2006年9月23日にM-V F7で打上。現在も運行継続中。
https://hinode.nao.ac.jp/gallery/latest/で太陽全面の最新X線画像を確認できる。
太陽フレアの観測、太陽風や磁気嵐の予測に係わる基礎データ収集で
太陽物理学に大きく貢献。
・MUSES-C(小惑星探査機)
2003年5月9日にM-V F5で打上。2010年6月13日に運用終了。
小惑星からのサンプルリターンに成功。長期間のイオンエンジン運用の実証。
・PLANET-C(金星探査機)
2010年5月21日にH-IIA F17で打上。500Nセラミックスラスタが破損し、
2010年に予定していた金星周回軌道への投入に失敗、2015年12月の金星再接近時に
姿勢制御スラスタを使用して金星長楕円軌道に投入し、変更した観測計画を実施。
2018年に定常運用は終了。2024年5月に通信途絶。
赤外線観測により、金星の地表面の物性や火山活動の有無を調査。
・BepiColombo/MMO(水星探査計画/水星磁気圏探査機)
2018年10月19日にAriane-5で打上。電気推進モジュールの電源が故障し、
イオンエンジンの推力を低減して運用中。2026年11月に水星到達予定。
これらは長期ビジョン発表時にはすでに計画が進行し、
人工衛星/探査機の設計・製造に着手していたものと考えられます。
「(2)月の探査と利用」でもSELENEについて言及されていますね。
・SELENE(月探査機)
2007年9月14日にH-IIA F13で打上。2009年6月11日に月面へ制御落下。
月周回軌道から月の表面や内部構造、鉱物組成に関する詳細なデータを取得。
高解像度の月地形データ、クレーター分布も取得。月の重力場の高精度測定も行う。
これらの言及された衛星/探査機の後にも、計画されて開発や運用されているものが
いくつもあります。
・SLIM(小型月着陸実証機)
2023年9月7日にH-IIA F47で打上。2024年1月20日に月面へ軟着陸。
誤差100メートル以内の精密着陸を達成
・XRISM(X線分光撮像衛星)
2023年9月7日にH-IIA F47で打上。
強い重力場に付随する高温プラズマや加速荷電粒子から放射される
X線を分光撮像することで銀河と銀河団のエネルギー物質循環や
ブラックホールによる赤方偏移の観測が可能となった。
ただしResolveの保護膜が閉じた状態で当初の予定性能は出せていない。
・ERG(ジオスペース探査衛星)
2016年12月20日にイプシロンロケット F2で打上。
SPRINTバスを使用。ヴァン・アレン帯の観測を目的としている。
ヴァン・アレン帯は2000~5000kmと10000~20000kmに分布し、
衛星は軌道傾斜角31度、近地点460km、遠地点32110kmの楕円軌道で
ヴァン・アレン帯を通過する形で
高エネルギー電子の生成と消失過程を詳細に観測した。
・SPRINT-A(惑星分光観測衛星)
2013年9月14日にイプシロンロケット TF1で打上。NEXTARバス。
惑星大気観測に特化した極端紫外線望遠鏡を搭載し、
イオプラズマトーラスの形成とその変動、地球型惑星と太陽風の相互作用、
惑星磁気圏の動態、惑星の大気流出などを観測。2023年12月8日に停波。
近地点950km、遠地点1150km、傾斜角31度。
・EQUULEUS(地球・月ラグランジュ点探査CubeSat)
2022年11月16日にSLS Block1のピギーバックで打上。CubeSat 6U。
2023年5月18日に通信途絶。地球接近時の光学観測により無制御状態を確認。
<とりあえずの感想>
前回も言及しましたが、人工衛星/探査機は計画のスパンが長いため、
こういった長期ビジョンにおいても前半部分は具体的な計画で埋められる
傾向が強いように思います。
観測衛星や探査機も想定以上の科学的成果をあげることができており、
欧米の宇宙機関や大学などと観測機器の相互相乗りなどで強力もしているため、
トップといえるかどうかはともかく、世界的なサイエンスセンターとして
活動できているのではないかと思います。
「太陽系外への到達」というのはなかなか難しいかもしれません。
やはりボイジャー探査機のRadioisotope Power Systemのような
セラミック状(酸化プルトニウム(IV))に加工したプルトニウム238を用いた
原子力電池(正確にはゼーベック効果を用いた放射性同位体熱電気転換器)を
搭載することは、日本の探査機ではかなり難しいのではないかと思います。
※無事に地球を離脱する軌道へ到達できればよいですが、
打上時にロケットを指令破壊した場合は日本近海やその延長線上に
酸化プルトニウムの粉をまくことになり、
日本社会の放射性物質アレルギーを考えると厳しいものがあります。
また、「太陽系外の地球型惑星での生命の徴候の探索」ですが、
こればかりは運という要素もありますし、手段も具体的ではないので、
夢のある話、ということで記載されたのかな、と思っています。
「月面拠点の構築と利用のための技術を確立」
「月やラグランジュ点を人類活動の場として活用する"深宇宙港構想"の実現」
このあたりはかなり予算が必要になりますね。
低予算のプランとしてCubeSat(6U)で地球=月のラグランジュ点に到達する計画
などがありましたが、ミッション継続が難しい可能性が高い状態です。
とにかく月も地球=月ラグランジュ点もひたすら遠い上に、
人間が行く場合は日数を短くしなければならない(長くなればなるほどペイロードが膨らむ)ため
スイングバイでちまちまΔVを節約するような軌道もとれず、
国内最大の軌道輸送系のH3でもやっていくのはなかなか厳しいものがあるかと思います。
(軌道間輸送機の話が輸送システムの方であがっているので詳しくはそちらで)