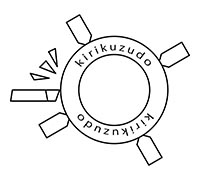切屑堂 kirikuzudo
ブログ: 2024/12/29 『JAXA長期ビジョン -JAXA2025- 20年後の日本の宇宙と航空』を読む(その3)
前回(その2)
ようやく各論に入っていきます。
<今回読んでいく対象領域>
今回は「長期ビジョン全体ロードマップ」から対象領域
1.宇宙利用による課題解決型の社会システム
を選んで見ていきたいと思います。
<「宇宙利用による課題解決型の社会システム」のロードマップ記載>
ロードマップには
2005~2015年
A「災害・危機管理に関する観測精度と頻度の向上」
B「気候変動に関する正確な観測手段の確立」
2015~2024年
A「高頻度高分解能観測による予報能力の向上とモバイル警報・予報の配信」
B「亜大陸レベルの評価と地域別政策への反映」
2025年
A「災害・危機管理情報収集通報システムの実現とアジア・太平洋地域への展開」
B「政策ツールとしての観測・予測統合、地球環境監視システムの確立」
とあります。
<「長期ビジョン」内の記載>
2章の「長期ビジョン」ではPage.8~9の
「(1)安全で豊かな社会の実現への貢献」が該当する部分です。
A「災害・危機管理情報収集通報システム」
B「観測・予測統合地球環境監視システム」
を実現することで、
「紛争や災害などから国民の生命や財産を守り、我が国の安全の確保を図る」
「そのために宇宙という場の活用を図る」
という書き方がされています。
<「ビジョンの実現に向けて」内の記載>
3章の「ビジョンの実現に向けて」ではPage.18~21が該当しますが、
前項のAとBはPage.18にそれぞれ
「観測衛星、通信衛星及び測位衛星等を用いてダイナミックに変化する国土空間情報を収集」
「二酸化炭素(CO2)濃度や降水などの地球環境変動に重要なパラメータについて、観測衛星による遠隔計測データと地上・海上などの現場観測データを融合」
と書かれており、
この時点でこれらは JAXA第一宇宙技術部門 の所掌範囲だな、とわかりますね。
JAXA第一宇宙技術部門 組織図 - サテナビ(JAXA)
https://www.satnavi.jaxa.jp/ja/about/index.html
<JAXA第一宇宙技術部門の人工衛星>
JAXA第一宇宙技術部門 の当該期間における運用人工衛星をそれぞれAとBに割り振ると下記のようになると思います。
A「災害・危機管理情報収集通報システム」の対象となる人工衛星
・ALOS-2(陸域観測技術衛星2号)
・ALOS-3(先進光学衛星)
・ALOS-4(先進レーダ衛星)
・QZSS(準天頂衛星)
・JDRS-1/LUCAS(光データ中継衛星/光衛星間通信システム)
・DRTS(データ中継技術衛星)
・SLTAS(超低高度衛星技術試験機)
・ETS-VIII(技術試験衛星8号)
・WINDS(超高速インターネット衛星)
・ALOS(陸域観測技術衛星)
・OICETS(光衛星間通信実験衛星)
B「観測・予測統合地球環境監視システム」の対象となる人工衛星
・GPM/DPR(全球降水観測計画/二周波降水レーダ)
・GOSAT(温室効果ガス観測技術衛星)
・GCOM-W(水循環変動観測衛星)
・GCOM-C(気候変動観測衛星)
・GOSAT-2(温室効果ガス観測技術衛星2号)
・EarthCARE/CPR(雲エアロゾル放射ミッション/雲プロファイリングレーダ)
・TRMM(熱帯降雨観測衛星)
・ADEOS-II(環境観測技術衛星)
<各人工衛星と具体的なビジョンの実現項目の紐付け>
「ビジョンの実現に向けて」のPage.20~21にわりと具体的な文言が登場しており、
Page.20の「衛星基幹技術の発展」の項で列挙されている技術はほぼ運用された衛星で
カバーされているような形になっています。
・高解像度光学観測技術 => ALOSシリーズ
・合成開口レーダ技術 => ALOSシリーズ
・移動体衛星通信技術 => ETS-VIII、WINDS
・高速衛星通信技術 => OICETS、JDRS-1/LUCAS
・高精度測位技術 => QZSS
・気象環境観測技術 => ADEOS-II、TRMM、GCOM、GPM/DPR、GOSAT
・衛星間通信技術 => OICETS、DRTS、JDRS-1/LUCAS
Page.21の「目標とロードマップ」は10年後と20年後に分かれています。
こちらも10年後の項はわりと対応できているものが多いのではないでしょうか。
・超小型携帯端末の実証 ×
=> ETS-VIIIのLNA-PS故障で未実施、後継計画はナシ
(2024年にSpaceXのStarlinkとAmazonのKuiperでとどめを刺される)
・小型アンテナに対する大容量伝送 ○
=> WINDSでKaバンドでの小型アンテナ(45cm)に対する622Mbps伝送を実証
WINDSでフェイズドアレイアンテナでのKaバンド通信を実証
JDRS-1/LUCASでNICT光地上局との光リンクを実証
・高精度測位技術(メートル級精度)の確立 ○
=> QZSSのCLASで繊値メートル級精度を達成
https://qzss.go.jp/technical/system/l6.html
・高分解能高頻度の災害観測 ○
=> ALOSシリーズで複数の災害観測とデータ提供を実施
・越境大気汚染/越境海洋汚染の常時観測 ○
=> GCOM-Cの多波長光学放射計SGLIでPM2.5の観測
GOSAT-2のマルチバンドイメージャでCO2,CH4,PM2.5,煤の観測
・可視赤外放射計、マイクロ波放射計、レーダ等による気候変動の継続観測 ○
=> GCOM-W、GPM/DPRでの水循環と気候変動の観測
20年後の項はどちらかというと行政側や政治外交側の要素が強くて、
これはJAXAの所掌範囲を超えてる気がします。
・10m分解能の静止地球観測衛星 ×
=> ひまわり8号で分解能500[m]
(ALOS-4の高度628km(太陽同期準回帰軌道)の高分解能モードで
分解能10[m]なのでさすがに静止軌道からは辛すぎるような気がする)
・「災害・危機管理情報収集通報システム」の実現
=>内閣府のお仕事……
・これらのアジア太平洋地域への展開
=>政治外交のお仕事……
・日常的な行政に組み込まれた政策ツールとしての「観測・予測統合地球環境監視システム」の確立
=>省庁のお仕事……
<とりあえずの感想>
DS2000バスや打上時4~5tonクラス(静止化2tonクラス)になる
人工衛星のプロジェクトは計画開始から10~20年スパンのものが多いようなので、
ロードマップ前半については「既に計画していて実現予定のもの」を
うまくまとめたような表現になっていると感じました。
また、ロードマップ後半の記載は「自分たちの衛星が観測したデータを適切に
政策や行政に反映してほしい」という意見のようにも見えます。
また、ETS-9が開発中で今後はホールスラスタ全電化バスが標準になる方向ですが、
「低軌道コンステレーションと地上通信網の組合せではできないこと」
を求められていく流れは強くなると思います。
IHIエアロスペースが担当しているETS-9の国産ホールスラスタも苦戦していたようで、
「ETS-9を確実に静止化させるためには、主系としての信頼性を保証するための十分な試験データが得られていないと判断」
「軌道上実証機器に位置づけを見直し」
ということで、海外製の実績あるホールスラスタを採用することになったようです。
技術試験衛星9号機(ETS-9)の開発状況について(2021年6月28日) - 宇宙開発利用部会
https://www.mext.go.jp/content/20210628-mxt_uchukai01-000016488_12.pdf
三菱電機の担当したフルデジタル通信系はわりと順調なようですね。
スターダストプログラム「衛星用の通信フルデジタル化技術開発」成果報告(2024年6月28日) - 宇宙開発利用部会
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/02-jissyou/jissyou-dai29/siryou2-1.pdf
「(その4)」へ