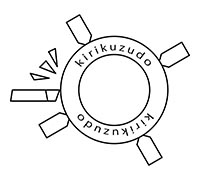切屑堂 kirikuzudo
ブログ: 2024/12/29 『JAXA長期ビジョン -JAXA2025- 20年後の日本の宇宙と航空』を読む(その2)
前回(その1)
<前提としての、ここ20年の大きな変化>
20年の振り返りになるので、航空宇宙に限らず日本における
社会・政治・経済・技術での大きな変化を列挙しておかないと
適切にこのビジョンを振りかえることができないと思うので、
とりあえず思いついたものを挙げていきたいと思います。
A:インターネットの通信帯域
2004年のInteropのShowNet(当時の最先端ネットワーク展示)ですが、
エクスターナルの接続は10GbE x 4回線で 40Gbpsでした。
2024年のエクスターナル接続はNTT-Comに対して1.8Tですね。
Interop 2024 ShowNet
https://www.interop.jp/2024/shownet/concept/
総務省の統計でも2023年11月の
固定系ブロードバンド契約者ダウンロードトラヒック推定量は
34.5Tbps(1日あたり355.6PB)になっています。
我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計結果(2023年11月分) - 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000929698.pdf
2004年にこのトラヒック量を予測できたかというと少し厳しいですね。
クレイジーです。
B:スマートフォンと広帯域移動通信
先ほどの総務省の統計で2023年11月の
移動通信ダウンロードトラヒック推定量は7.0Tbpsになっています。
2003年の移動体通信、「AirH"」とかみなさん覚えていますか?
PHS回線で32kbpsが出て定額制ということで、Operaブラウザを搭載した
折りたたみ携帯PHS端末を購入してワイワイしてた記憶があります。
条件さえ良ければいまどきは携帯端末で100Mbpsの帯域が確保できるんですよね。
256QAMの変調がコンシューマで実現できるなんて誰が想像したかという話です。
Windows Mobileを搭載した携帯通信端末としてS01SH(EM-ONE)が発売されたのは
2007年ですね。こちらも購入してSSL-VPN端末として使ったりしていました。
そして、iPhone 3Gが発売されたのが2008年。
C:Google、Amazon、Twitter、Facebook、Apple
インターネットの広帯域化と高機能携帯端末の普及で
HTTP(S)ベースのサービスを展開する企業が大きく躍進したのもここ20年ですね。
新聞・テレビ・週刊誌などのマスメディアとリアル空間での口コミが主たる情報源でしたが、それが大きく変化しました。
専門知識も、専門書を読み解いたうえで実務経験が必要であったものが、
YouTubeなどの動画による解説でハードルが低下し、
知識伝達に必要なコストが低下する分野も出てきました。
D:政治と経済の動き
2008年にリーマン・ショック(サブプライム住宅ローン危機)、
2009年に民主党政権が成立し、2011年3月11日に東日本大震災が発生、
2012年に習近平が総書記に、2011年の"アラブの春"から
2013年のイスラミック・ステートが台頭、
2014年にロシアによるクリミア半島侵攻、
2020年の英国EU離脱、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻、
というように、大きな変化がありました。
航空宇宙分野に直接的に影響があったものもあれば、
そうでないものもありますが、一応おさえておきたいところです。
E:新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)
SARS-CoV-2による感染症が2020年から流行し、現在も収束する様子はありません。
F:気候変動と再生可能エネルギーの普及
気候変動に注目が集まり、太陽光発電と風力発電を中心とした
再生可能エネルギーが普及しました。
人類のエネルギー獲得に占める割合はまだそれほど大きくないですが、
現状の技術で達成可能な限界に近いところまで普及した状況ではないでしょうか。
G:HEMTの普及による送信機の固体化
HEMT(高電子移動度トランジスタ)の技術開発が進んだことで
Sバンド、Xバンドなどでも相応の高出力な送信機を
固体化することが可能になりました。
人工衛星コンステレーションや地上局の小型化に
大きな影響があったかと思います。
H:コンピュータの演算能力向上の方向性の変化
プロセスルール微細化による性能向上の限界が見えてきたところから
多数のプロセッシングユニットを用いる方向で
コンピュータの演算能力を向上させようという流れが
2000年代半ば頃から見られました。
2007年には既にNVIDIAはCUDAの提供を開始していますし、
2007年にSUNが発表したUltraSPARC T2は64スレッドを処理できる構成でした。
I:電動アクチュエータの性能向上
気候変動への注目から二酸化炭素排出量を低減しようという動きが強くなり、
内燃機関を動力とするものや油圧機器などの電動化が進みました。
背景として、プロセス微細化の恩恵によるパワー半導体の
大電流処理能力の向上とMCUの性能向上による
電動アクチュエータの励磁電流制御の発展があるかと思います。
J:積層造形技術
各種特許が2009年に切れたことで積層造形技術が普及しました。
造形コスト/造形サイズ/造形時間/表面粗さに課題は残るものの、
複雑な形状の金属構造物を高密度で成形可能ということで、
既に各所で利用が進んでいます。
とりあえず、このあたりが20年間の大きな変化というあたりでしょうか。
※何か思いついたら追記するかもしれません。
※2024/12/31
複数のフォロワーさんから「忘れてますよ!」とご指摘があったので追記
<2024/12/31追記分>
K:電池技術
リチウムイオン電池に代表される二次電池のエネルギー密度/出力密度が
大きく向上しました。
円筒型リチウムイオン電池(18650)は1992年200[Wh/L]のエネルギー密度だったものが、
2010年には600[Wh/L]、2022年には800[Wh/L]まで到達するものも発表されています。
日本エネルギー学会機関誌「えねるみくす」Vol.97 No.4(2018年)より「リチウムイオン電池の開発」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jieenermix/97/4/97_335/_pdf
(図4 円筒型リチウムイオン電池(18650)のエネルギー密度の変遷)
Enpower Greentech プレスリリース Enpower18650 389[Wh/kg]を達成
https://www.enpower-greentech.com/assets/news/pdf/20221104_jp_enpower-news-release_japanese_20221104.pdf
電池のエネルギー密度/出力密度が向上したことにより、
電気自動車が実用域になりましたし、携帯端末の演算能力に関する制約も緩和されました。
L:メタマテリアル
微細加工技術の発展から赤外/可視光領域のメタマテリアルが
実現されるようになってきました。
1968年に負の屈折率を持つ材料が提案されてから長い期間を経て、
2000年頃には負の透磁率を示す分割リング共振器と
負の誘電率を示す直線微細構造の組合せによりマイクロ波領域で実証されました。
最近では市販品のシートなどが市販されるようになっています。
周期的微細構造により赤外線波長を選択放射する放熱シート - オキツモ
https://www.okitsumo.co.jp/product/vsi/
また、振動音響に対してもメタマテリアルが実現されてきています。
微細共振器による超音波透過メタマテリアル - 村田製作所
https://article.murata.com/ja-jp/article/what-is-a-metamaterial
</2024/12/31追記分>
思ったより長くなったので、「長期ビジョン全体ロードマップ」から対象領域
1.宇宙利用による課題解決型の社会システム
を選んで見ていくのは次回にしたいと思います。
「(その3)」へ