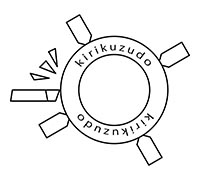切屑堂 kirikuzudo
ブログ: 2024/12/29 『JAXA長期ビジョン -JAXA2025-』を読む座談会のために手元に展開した参考書
「『JAXA長期ビジョン -JAXA2025- 20年後の日本の宇宙と航空』を読む」シリーズの初回
『JAXA長期ビジョン -JAXA2025- 20年後の日本の宇宙と航空』をネタに
座談会みたいなのをTwitterのスペース機能でやることになりました。
主催は @dirG さんで、スピーカー参加します。
<手元に展開した参考書>
航空宇宙関係の専門家というわけではないので、
どちらかというと他の方がカバーしていないさそうな範囲の発言を
したほうがいいな、と判断して、書庫から本を抜き出してきました。
01.『ネクスト・ソサエティー』(P・F・ドラッカー著、ダイヤモンド社)
2002年に出版されたドラッカーさんの著書の日本語版ですね。
いま読んでも含蓄に富んでいます。
・雇用形態の変化
・市場の変化(若年人口の急減)
・高度の競争社会(知識社会化)
・保護主義の復活
・人口構成の変化
このあたりの記述は参考になりそうです。
02.『都市の原理』(ジェイン・ジェイコブズ著、鹿島出版会)
都市研究家ジェイン・ジェイコブズの著書の日本語訳です。
「都市起源論」という章がお気に入りで、
農業の余剰生産が都市をつくったという通説を否定し、
狩猟採取と交易を起源としています。
「都市」という概念は地球外でも適用可能なので、
これを援用していきたいと思います。
03.『「情報の歴史」を読む ~世界情報文化史講義~』(松岡正剛著、NTT出版)
『情報の歴史』という本を解説した本です。
"情報"という概念をコアに人類史の年表を書き起こしたもので、
なかなかすごい本なのですが、
この解説本もとにかく広範な分野を"情報の編集"という概念で
バッサバッサと切り捨てていくような面白さがあります。
このスケールの大きさは定期的に触れておきたいものですね。
04.『富の未来』上下巻(アルビン・トフラー著、講談社)
2006年に出版された、未来学者アルビン・トフラーの著書の日本語版です。
こちらも様々な分野の過去と現在に言及しつつ、近い将来の流れについて語っています。
上下巻の目次だけでも圧巻ですね。
<上巻>
富の最先端、欲求が生み出すもの、富の波、基礎的条件の深部、速度の違い、
同時化産業、リズムが乱れた経済、時間の新たな景観、大きな円、
高付加価値地域、活動空間、準備が整っていない世界、逆噴射、宇宙への進出、
知識の先端、明日の「石油」、死知識の罠、ケネー要員、真実の見分け方、
研究室の破壊、真実の管理者、結論-収斂、隠れた半分、健康の生産消費者、
第三の仕事、来るべき爆発的成長、さらにあるタダ飯、音楽の嵐、
「生産能力性」ホルモン、結論-見えない経路
<下巻>
変化の教え、内部崩壊、ボルトの腐食、コンプレクソラマ、セプルベダの解決法、
結論-頽廃の後、資本主義の終幕、資本の変換、不可能な市場、明日の通貨、
貧困についての時代後れの見方、明日に向けた複線戦略、貧困の根を絶つ、
中国はまたも世界を驚かせるか、日本のつぎの節目、韓国の時間と衝突、
ヨーロッパの失われたメッセージ、アメリカの国内情勢、アメリカ国外の情勢、
目に見えないゲームのゲーム、終わりに-始まりは終わった
ヘラクレイトス
「同じ川に二度足を踏み入れることはできない。二度目には川が変化してるからだ。」
こちらは"富"という概念で様々な分野を取り扱っていますが、
特に非経済的な"富"についてもバランスよく触れているのが面白いところです。
05.『月をマーケティングする ~アポロ計画と史上最大の広報作戦~』(デイヴィッド・ミーアマン・スコット&リチャード・ジュレック著、日経BPマーケティング)
マーケティング/PRという面からアポロ計画を取り扱った著書です。
独裁国家ではない限り、大衆の動向に無縁な目立つ国家プロジェクトは
あり得ませんから、そういった大衆の動向をどうやって引き寄せるか、
ということは有史以来続けられてきた行為です。
大衆が情報発信可能となった2025年、重要度は変わらないでしょう。
06.『浮体式海上空港 ~巨大プロジェクトへの挑戦~』(マリンフロート推進機構編、鹿島出版会)
利用可能な国土空間には必ず住民がいる上に飛行経路上には間違いなく都市や町がある、
といった本邦が今後、航空宇宙分野でそれなりの存在感を示すには
海洋利用をうまくやっていくしかないわけでして、そのひとつとして
「浮体式海上空港」の概念は有効なのではないか、ということから手元に置きました。
07.『イノベーションのジレンマ ~技術革新が巨大企業を滅ぼすとき~』(クレイトン・クリステンセン著、翔泳社)
製品戦略分野の古典ですね。日本語版は2001年に出版されています。
続刊の『イノベーションへの解』も含めて、航空宇宙分野にも適用可能な
いろんな枠組みがあるので、こちらも手元に置いて話をしたいと思います。