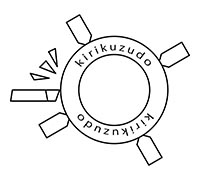切屑堂 kirikuzudo
ブログ: 2025/09/28 設計という言葉が含む範囲について
(会合でめちゃくちゃ飲まされた帰りの新幹線の中で書きました)
「設計」がお絵かきだと思ってる人が多すぎる問題。
あるいは中途採用の方が「設計やれます」といって入ってきたのに、
3Dお絵かきしかできなかったのでツラいというお話。
<問題を解く、という姿勢>
設計の基本は「問題を解く」というところにあると思っていて、
なんなら大きな問題を解く為に小さな仮説を設定して
それを解くのも設計の範囲だと思います。
(自分としては)未知の問題に遭遇した場合は、
正誤はともかくとして自分の考えうる仮説と解を提示するところまでが
お仕事なんではないかと思っています。
(なんなら簡易的な試験も設計の仕事だし、
試験治具とDUTを考えるのも設計の仕事だと筆者は思ってます。)
<問題の次数を減らす>
はじめての問題に遭遇した場合、あるいは困難な問題に遭遇した場合に大切なのは、
「自分が扱い得る範囲に問題を切り分ける」という態度かと思います。
もちろん問題を切り分けることで、分けた問題を接続するという新たな問題が
生まれるわけですが、とりあえず「手が動かせる状態」とすることは、
モチベーションの面からも大事だと思います。
問題を切り分けるのには大きさを切って小さくする以外にも、
「問題の次数を減らす」という手があります。
5年前に流行った1D-CAEなどはまさに次数を1Dにまで落として取り扱う手法ですし、
3D-CADではなく、代表的な断面を2D-CADで検討するだけでも
扱いやすさはかなり違います。
※2000年頃の古の2chでも語られていましたが、
「3D-CADは作るものがわかってる状態じゃないとロクなことにならない」
というのは、3D-CADが普及したいまだからこそ
大事にしたい一言かと思います。
問題の次数を減らすという手法でいうと、技術史でも天才的な例があります。
境界潤滑におけるレイノルズ方程式がそれで、
実体としては3次元の滑り軸受の問題を2次元の微小寸法問題として扱うことで、
Navier-Stokes方程式のうち36項を3項に圧縮した例がそれです。
『トライボロジー再論』に「レイノルズの天才」というそのままのタイトルで
その内容が記載されていますが、これはまさに天才の所行といえましょう。
ここまで天才的なことは凡才の我々には難しいですが、
それでも問題の次数を減らすという態度がいかに重要かはわかると思います。
レイノルズという工学史上の天才ですら次数を減らすことで
難問に向き合うのですから、いわんや凡人をや。
<根拠を示す>
ありとあらゆる設計判断に根拠を示すことは困難ではありますが、
やはり線を一本引くたび、あるいはモデルに寸法を入力するたびに、
我々はなんらかの判断を行っているわけです。
筆者の場合は現場が長かったので、
入手性のよい材料の寸法やどこでもお願いできる汎用的な加工法、
多少の加工のズレを吸収できる設計上のマージンなどを重視する傾向があります。
それと並行して、曲げと座屈を主とした構造の健全性の検討も入ります。
荷重の流れが見えるレベルにはありませんが、少なくとも、
どの部材が主にどのようなタイプの荷重あるいはモーメントを負担しているかは、
ざっくりとでも考えているのではないでしょうか。
クリティカルな部分になればとうぜん手計算や簡易的なFEAツールを適用して
相応なマージンが得られているかを検討します。
とにかく重要なのは「なんでこういう形状になっているのか」という問いに
回答できることかと思います。
直観というのもわりと馬鹿になりませんので、
どう考えても安全そうならそれはそれでありとは思いますが、
直観が裏切られた例も工学史上では多々あります。
そういう事例を知っているのも、工学教育の賜物とはいえるでしょう。
※「コメット、タコマ、リバティ」を知らないやつはモグリだ、
と失敗学の畑村教授が『機械創造学』で書いてましたね。
あと、JISをはじめとする世の中の標準規格や法令などは
業界諸賢がかなりの労力をかけてまとめたものなので、
それを根拠とするのは正しい行為かと思います。
<これは自分が解決しなければならない問題なのだ、という姿勢>
どれだけ能力があったとしても、
当該の問題を「とにかくこれは自分が解決しなければならない問題なのだ」と
捉えることができなければ、結果につながらないのではないかと思います。
もちろん、世の中には同じ問題をどこかで誰かが解いているはずではありますが、
それがそっくりそのまま、あなたの前に示される可能性は限りなく低いです。
※どこまでをそっくりそのままかという話はありますが、
筆者の認識としては規格類にはわりとそっくりそのままがたくさんあるので、
このあたりは応用するための嗅覚みたいな話になるんでしょうね。
いま目の前にある問題はとにかく自分が解くのだ、
という態度は少なくとも工学的課題が相手であれば人生においては
無駄になることはないので、積極的に向き合っていきたいものです。
※自分は中学生のときに、同級生の持っていた塾の数学の課題を解くなかで
この感覚を養ったように思います。
新規性がバリバリの課題なんか、一線の研究者ならともかく
我々凡人の前に降ってくることはほぼないんで、
組み合わせとか問題の切り分けとか
問題の次数を落とせばなんとかなる話は多いです。
※物理的に無理なネタもありますが、
そういう話は理詰めで殴り返せばよろしいかと。
<お絵かきと設計の差>
筆者は現場が長いのでとくにここが差を感じるところですが、単なるお絵かきは
「どういう素形材をどういう工作機械で
どうやって加工してどうやって組み立てるのか」
「そのときに図面(あるいは3Dモデル)からどれだけズレるか」
「物理的に成立するか」
という考慮が欠けていると感じることが多いです。
3Dモデルには重力が作用していないので、
段付きシャフトじゃなくてもローターが落ちてこないけど、
それ、現物だったら重力でローター落ちるよね、みたいな、
こいつ義務教育おわってんの?みたいな話も、まあ、あるんですよね。
(その瞬間、正直、こいつに給料はらいたくねえな、ってなりました。)
旋盤もボール盤もフライス盤も溶接もはんだ付けも鋳造もやすりがけも
組立調整も経験せずに「設計でござる」とか言っていいのは
頭にデキがちょっと違う方だけなんですよね。
お前はそんなに頭のデキがよろしいのか。
へーしゃにきてる時点でお察しであろう、と。
<現物・現場>
フッ軽、大事。現物と現場の情報量はやばいよ。
みんな椅子にケツが貼りついてるのかな。
温度、音、振動、匂い、計測器の時間的変化、それらのセンシング・フュージョン。
現場に行って現物を見ましょう。
実際の実務上は全部を自分でやるわけにはいかないんですが、
作業をした方が感じた違和感が気軽に自分に伝わるようにしておいたほうが
いいとは思います。そういう面でも現場には顔を出したほうがいいんですよね。
フッ軽、大事。
<工学的コモンセンス>
どれだけ現場に行っても認識するためのフレームがなければ
情報量に圧倒されるか、何を見たらいいかわからずに終わるだけになりますよね。
学生時代には教官に「君らは工学的センスがない」と散々いわれたものでありますが、
いま言い換えるなら、それは「工学的コモンセンス」とでもいうものなのかな、と。
経験も大事なんですが、やはり認識のフレームがなければ経験を糧にできないわけで、
ここは「工学書を読め」という感じになるわけです。
ただ、漫然と工学書を読んでいてもなんともならないので、
「問題をなんとかしたい」
=>「解決方法を探して工学書を読み漁る」
=>「それっぽいネタがあったので試してみる」
=>「新たな課題が見つかる」(以下ループ)
みたいなのをやっていかなきゃいけないんですよね。
機械や電気や土木はこのループがとてつもなく時間がかかるのがつらいところですが。
(重厚長大産業は年単位、土木は十年単位)
<コストだけじゃない商売のことも考えなきゃ>
商売のことを考えるのは経営者とか営業部門とかのお仕事ではあるんですが、
それとも無縁ではいられないのが設計のつらいところ。
粗利益率と在庫回転率の積である交差比率という指標とかご存知でしょうか。
製品戦略の教科書に出てきますが、部品在庫と粗利益の積は
事業が成立するかどうかに直結するレベルの重要な指標です。
(かつての百貨店は店舗ブランド力x高い粗利益率x低い在庫回転率で
利益を確保していたが、ホムセンや通販が低い粗利益率x高い在庫回転率で
事業を成立させつつ前者を駆逐した、みたいな)
設計者はとにかく目先のコスト削減に走りがちですが、
多少はコストがかかっても在庫回転率がいいほうが
経営者にとってはありがたいことが多いんですよね。
在庫って現金が眠って負債(負の利益率を生むもの)になってる状態なんで。
鋳物とか最小ロット数が多い部品とかは
経営者にとってはできるだけ避けたい選択肢です。
倉庫代や場所チャージだってタダじゃないんで。
でも鋳物みたいなのは余所がやらないゆえに、
製品競争力+高い粗利益率の源泉でもあったりして、
なかなかこのあたりの判断は難しいところではあったりします。
で、デキる設計者はこのへんの案配も絶妙なんですよね。
商売の勘みたいなのもあるというか。
グロービスの教科書を読んだりすればわかる話ではあるんですが、
そこは設計の範疇から外しちゃう方が多いんですよね。
まあ、しゃーないです。筆者もネットワークSEの経験なければ知らなかったし。
<かなり知らなきゃいけないことが多い>
感覚的な話になりますが、設計は商売の上流から下流のほぼ真ん中にあるので、
上流側も下流側もどちらも広く見渡せなきゃいけない職種という気がします。
あと、なんだかんだで現場にも行って服と手を汚さなきゃいけないことも多く、
机でパソコンさわってればいいみたいなイメージをもってると
ツラいんじゃないでしょうか。
「設計」がお絵かきだと思ってる人はちょっと認識を改めたほうがいいかと思います。
---------------------------------------